ジェイテクトサーモシステム事例Rescale で誘導加熱解析の高速化・効率化を実現し、顧客の要請に即日対応可能に。
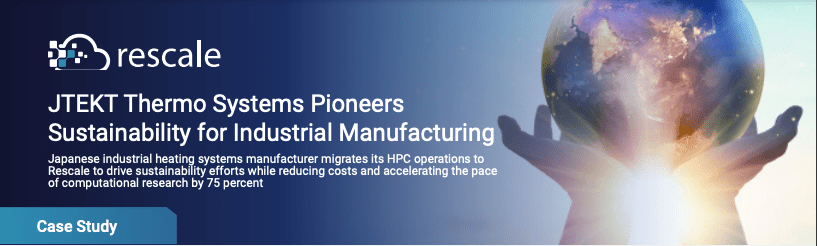
ジェイテクト サーモ システムズは、1967 年以来、産業用暖房システムの世界をリードするメーカーです。その歴史を通じて、イノベーションは組織の成功の重要な要素でした。
業界の最前線であり続けるために、ジェイテクトは自動車、半導体、エネルギー、通信市場向けの加熱システム、オーブン、炉を継続的に改善する必要があります。
しかし今、ジェイテクトはおそらく最大の課題に直面している。 産業用暖房システムをよりクリーンでエネルギー効率の高いものにする必要があります。 メーカーによるエネルギー集約型の加熱システムの使用方法における画期的な進歩は、より環境に優しい産業プロセスの構築において大きな前進を意味する可能性があります。
同時に、より効果的な暖房システムを構築しながら、エンジニアリングコストと製造コストを削減し続けなければなりません。
しかし、Rescale と提携することで、大阪に本拠を置くこの企業は、より迅速かつ効率的にイノベーションを行えるようになり、イノベーションのペースを 75% も加速することができます。
詳細については、ケーススタディの全文をお読みください。
